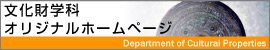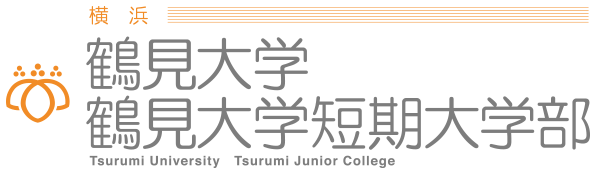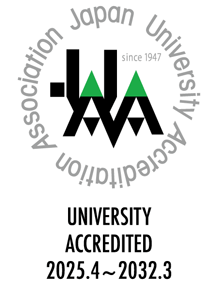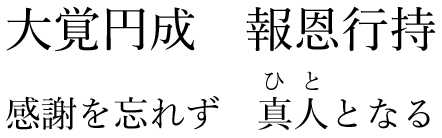キャリア・就職支援
生涯学習・司書講習
入試情報
基礎概説科目[専門必修科目]
文化財の基礎を学ぶ
- 文化財研究法:多彩な文化財を解説
- 地理学:自然と人間の関係を探る
- 考古学:遺跡・遺物で人類の歴史をたどる
- 文化人類学:人類の社会を考える
- 博物館概論・博物館経営論:文化財の研究・保存・活用を考える
- 歴史資料購読:古文書・古記録を読むために
専攻科目群[専門選択科目]
系列を選び深く学ぶ
歴史・地理系列

- 日本史Ⅰ・Ⅱ
- 日本文化史Ⅰ・Ⅱ
- 古文書学Ⅰ・Ⅱ
- 日本仏教史Ⅰ・II
- 歴史地理学
- 歴史地誌学
- 日本史概論/世界史概論/地誌学概論/宗教学概論
考古・美術系列

- 先史考古学
- 歴史考古学
- 日本美術史Ⅰ・Ⅱ
- 建築史Ⅰ・Ⅱ
- 工芸史Ⅰ・Ⅱ
- 史跡特論Ⅰ・Ⅱ
文化財系列
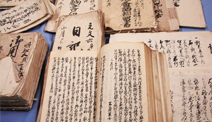
- 博物館資料保存論Ⅰ・Ⅱ
- 有職故実Ⅰ・Ⅱ
- 文化財各論Ⅰ~Ⅴ
- 博物館展示論
- 学外館務実習(学芸員課程履修者)
実習科目[専門必修科目]
実物で技術を磨く
※社会情勢により変更する可能性がございます
1年次


[実習ⅠA]
教室を出て文化財の所在地へ
春の1泊見学旅行のほか、鎌倉の古社寺や各地の民家、遺跡、博物館などを見学します。
[実習ⅠB]
弥生式土器の復元から図化、公表へ
破片となった弥生式土器の模造品を接合して完形にします。
2年次


[実習ⅡA]
古文書の補修技術まで習得
史料の扱い方、写真撮影や調書の作成、虫喰い穴の繕いや裏打ちなどを実習します。
[実習ⅡB]
発掘調査の実際に挑戦
専用の実習場に埋まった弥生時代の竪穴住居址を発掘し、測量機器を駆使して図面を作成します。
3年次


[実習ⅢA]
科学の眼で調べる
実体・電子顕微鏡、赤外線・X線透視検査装置、蛍光X線分析装置などで試料を分析します。
[実習ⅢB]
文化財をどのように見せるか
掛け軸や工芸品の取り扱い方法を学びます。文化財の現地見学も行います。
4年次


[実習Ⅳ]
多彩な文化財を解説
国外コース:ハワイ・カンボジア・インドなどを訪問。
国内コース:沖縄のグスク群や石見銀山、大内宿などを訪問。
自主コース:独自の研究テーマでコースを設定。四国八十八ヶ所巡りなどがありました。
演習科目[ゼミナール]
自分のテーマを追求する
個性あふれる教員と共に、調べる力・まとめる力・発表する力をつけ、卒業論文へ!
小林恭治教授(日本語史)
漢字や古辞書の研究
専門は古辞書ですが、典籍や石碑などの文字も研究。日本語史の視点から文字の歴史を探ります。
緒方啓介教授(日本美術史・博物館学)
仏教美術を探る
仏像を中心とした美術史が専門です。寺院や博物館などで多くの作品に出会いたいと思います。
星野玲子教授(文化財科学)
文化財の分析・保存
専門は石造文化財。ゼミでは各自のテーマについて文化財科学の視点から研究します。
矢島律子教授(美術・工芸史学)
美を求めたアジアの営みを探る
陶芸史を軸に中国・日本・朝鮮・東南アジア工芸史との交流を探ります。
田中和彦教授(考古学)
遺跡調査の魅力
貝塚遺跡や墓地遺跡を調査し、出土した陶磁器、土器の生産、流通、消費とその変遷を研究しています。
鈴木一馨教授(宗教学)
宗教の姿と文化財
多くの文化財に関わりがある宗教。その思想や宇宙観、宗教儀礼、宗教民俗、宗教的空間理念などを学びます。
近藤祐介准教授(歴史学)
戦国時代を考える
専門は中世寺院史で、その視点から戦国時代の社会や民衆と仏教徒の関わりなどを研究しています。
西澤美穂子准教授(歴史学)
江戸時代の対外関係
「鎖国」日本と世界の関わりを研究しています。ゼミでは近世史料の解読を中心に進めます。
上杉彰紀准教授(考古学)
古代都市の盛衰を探る
アジア各地の古代都市の盛衰を、人やモノの移動という観点から研究しています。

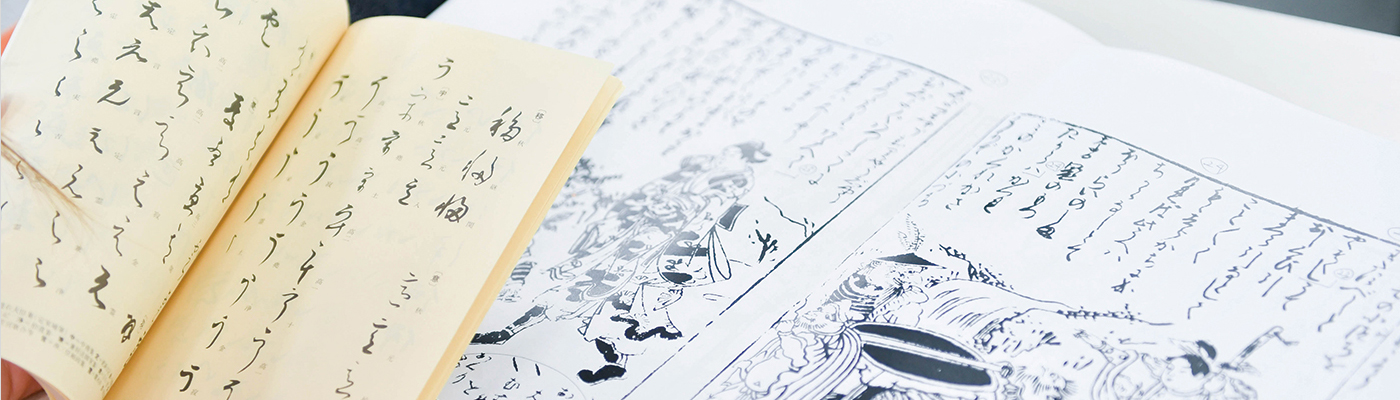
 デジタルパンフレット・資料請求
デジタルパンフレット・資料請求