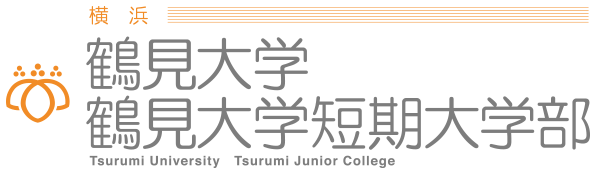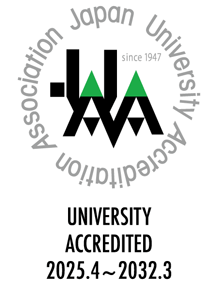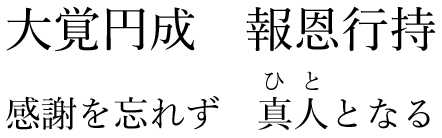キャリア・就職支援
生涯学習・司書講習
入試情報
 生涯学習概論
生涯学習概論
片岡 了:明治大学講師
生涯学習の主人公はほかでもない自分自身です。生涯学習を支援する側に立つ図書館員をめざす人であっても、一人の社会人として学ぶことで得られる経験も貴重な財産になるはずです。自らの学習経験をもとに、支援を受ける相手の立場に立って支援することができれば、よりよい図書館サービスが行なえるのではないでしょうか。さらに、支援する・支援される関係にとどまらず、学び合う相互的な人間関係を築いていくことも生涯学習の課題となります。
また、図書館員をめざす人の中には「本」が大好きな人が多いと聞きます。作品を介して作者と読者との間に出会いが生まれるように、本等の資料を通して利用者と図書館員との間に交流が起きることもあります。図書館はコミュニケーションの場ともなるので、「本」が好きな人は、同時に「人」が好きな人であってほしいと願います。生涯学習の理解をもとに、利用者の学びを支えながら、自らも学び続ける図書館員を目指してください。
 図書館概論
図書館概論
長谷川 幸代:跡見学園女子大学准教授
様々な図書館の在り方やサービスに目を向け、図書館がどのように社会での役割を担っていくのかを検討していきます。高度情報化社会の中で、図書館だからこそ提供しうる価値を理解することが求められるのではないでしょうか。そのために、この授業では図書館の社会的意義や伝統的な機能と新しい図書館の形態を重点的に取り上げます。また、デジタル化やネットワークの利用を伴う図書館の状況や社会動向に応じた取り組みについてもふれていきたいと考えています。
 図書館制度・経営論
図書館制度・経営論
加藤 好郎:愛知大学講師
講習では、図書館経営を自分で行うことを想定して、「利用者のための図書館サービスとは?」を考えてみてください。また、この講習への参加の目的は、受講生の方々と友達の輪を作ることです。現代社会のなかで、図書館員として仕事をするためには、隣の図書館、最寄りの図書館の職員の方々と情報を共有化することが不可欠です。つまり、ライブラリアン同士のネットワークを構築することです。
暑い!暑い!時期です。健康に留意して、お互いを励まし合って、和気あいあい、楽しい講習を楽しく乗り切ってください。
大谷 康晴:青山学院大学教授
私たちが経験する良いサービスに触れる時には、その裏側でさまざまな人たちの努力があります。この科目は図書館サービスそのものに触れることは少ないですが、その裏側を見ていくものだと思ってください。
 図書館情報技術論
図書館情報技術論
長塚 隆:鶴見大学名誉教授
図書館業務に必要な基礎的な情報技術を修得することを目標としています。コロナ禍のなかで図書館への情報技術の導入はより急速に進んでいます。講師自身の研究課題や国際会議での体験を交えて、コンピュータ等の基礎、図書館業務システム、データベース、検索エンジン、電子資料、コンピュータシステム等について、分かりやすく紹介します。
課題の検討を通じて、受講生の皆様が自分の意見・見解を持てることを目指します。
図書館総合展での講演も参考にしてください。
*先生のHPはこちら
 図書館サービス概論
図書館サービス概論
仲村 拓真:山口県立大学講師
「図書館サービス概論」は,「図書館概論」や「図書館制度・経営論」で学んだ理念や規定がどのように実践されているかを知るとともに,「児童サービス論」や「情報サービス論」といった各種サービス論を学ぶための基礎を身につけるための科目です。集中的に,オンライン講習として開催されますので,時間を確保したり,モティベーションを維持したりすることが大変だと思いますが,頑張ってください。そして,講習中,さらには,講習後に,時間を見つけて,いろんな図書館を訪れてみることをお勧めします。講習で学んだことが,各図書館でどのように実践されているか,観察してみることで,学びを深めることができるでしょう。
松林 麻実子:筑波大学講師
本講義はオンデマンド形式ですが,こまめなフィードバックや情報共有を心がけたいと思いますので,質問や意見があればいつでもお寄せください。
 情報サービス論
情報サービス論
野末 俊比古:青山学院大学教授
主体的・積極的な姿勢で臨むことを期待しています。
*先生のHPはこちら
 児童サービス論
児童サービス論
河西 由美子:鶴見大学教授
本科目は講義科目ですが、子ども読書推進の実践的なメソッドについて、演習的な要素も可能な限り取り入れたいと考えています。ぜひ積極的に参加してください。
 情報サービス演習(情報)
情報サービス演習(情報)
畑田 秀将:山形県立米沢女子短期大学准教授
情報検索は日常的にスマホやパソコンを用いてされているでしょうから、得意な方もいらっしゃるでしょう。改めて授業で扱わなくともよいのではないかと思われる方もいるかもしれません。ただ、普段私たちが行っている検索と業務として提供する検索とでは、その目的も方法も異ってきます。
情報サービスとして行われる検索に求められているものは、検索システムを適切に扱うことのできるスキルのみならず、利用者の個々の状況に応じた情報の選択です。単に答えをいくつか提示すればよいというものではありませんので、この点を意識しながら取り組んでみてください。
千 錫烈:関東学院大学教授
データベースって何?上手に検索できるかな?と、最初は少し不安に思うかもしれません。
最初は慣れないかもしれませんが、一歩ずつステップを踏んでいけば、必ずできるようになります。この授業で情報検索のスキルを磨き、司書として未来の図書館を支えましょう!
山川 恭子:鶴見大学実習技術員
この授業では、Web上の各種データベースを使いこなし、必要な情報を見つけ出す知識と技術を学びます。演習を進めていくうちに、Google検索で間に合うんじゃないか、ChatGPTを使えばすぐに答えが出るんじゃないか、と思われる方も出てくると思います。検索エンジンやSNS、生成AIは私たちの“知りたい”というニーズを素早く解決してくれる、非常に便利なものであることは間違いありません。ですが、正確な情報、信頼性の高い情報、専門的な情報を得るためには、まだまだ図書館や各研究機関、企業などが提供するデータベースに頼る必要があります。また、WebサイトやSNSでは得られないような知識を与えてくれる図書などの情報資源になるべくたくさん出会うためにも、資料検索の専門的な知識が求められます。この授業を通して、今よりももっと能動的に、積極的に情報を探すことの意義を知ってもらえれば、と思います。
 情報サービス演習(レファレンス)
情報サービス演習(レファレンス)
原田 智子:鶴見大学名誉教授
角田 裕之:鶴見大学名誉教授
宮原 志津子:相模女子大学教授
吉田 隆:神奈川大学国際経営研究所客員研究員
司書という専門職は、利用者へ図書や雑誌や情報等を提供するサービス業です。
現在の図書館では、印刷物から電子メディアまで多様な情報資源を扱います。コンピューターの活用能力と情報資源への理解を深めることはもちろん必要ですが、同僚や他館の司書の方々、そして利用者とのヒューマンネットワークも重要です。オンライン・オンデマンド授業であっても、講習を通じて豊かな知識やスキルの獲得を目指すとともに、新たな人々との出会いがあると思います。
講師一同、授業でお目にかかるのを楽しみにしています。
 図書館情報資源概論
図書館情報資源概論
小山 憲司:中央大学教授
図書館情報資源概論では、「利用者が求める情報」という視点から、「図書館が扱う(べき)情報資源」について、みなさんと一緒に考えていきたいと思います。授業は講義形式(オンデマンド)ですが、受講生のみなさんの積極的な学びを期待します。
司書講習会は長丁場です。上手に気分転換をはかりながら、乗り切ってもらえたらと思います。
 情報資源組織論
情報資源組織論
角田 裕之:鶴見大学名誉教授
図書館のテクニカルサービスである目録データの作成と主題組織化の理論を理解することを目標としています。資料を探すためにOPAC(Online Public Access Catalog)は、重要な道具のひとつです。OPACは目録データがなければ、なにも表示されませんし、分類記号や件名が付与されていなければ適切な検索ができません。図書館にとって目録データと分類・件名は必須です。連日暑い日が続きますが、身体に気をつけ、一緒に学びましょう。
 情報資源組織演習(目録)
情報資源組織演習(目録)
榎本 裕希子:明星大学講師
情報資源組織演習Ⅰ(目録)では、各種属性の記録に関わる目録規則を数多く学びます。授業期間は短いものの、次々に多くの規則を扱うため、「まだあるの!?」と戸惑うことがあるかもしれません。しかし、焦らず一つひとつ取り組んでいけば、困惑は次第に理解へとつながるはずです。
精一杯サポートしていきますので、一緒に頑張りましょう。
大蔵 綾子:鶴見大学講師
図書館の仕事に憧れる多くの人にとって、図書館の仕事と言えば、資料の貸出・返却やレファレンスのような直接サービスを思い浮かべることでしょう。これに対して、目録作成のような間接サービスに思いをいたすことのできる人は少ないと思います。
しかし、利用者が入手したい資料に速やかに辿り着くことはできるのは、目録が正しく作成されてこそです。しかも、目録作成は、職人気質を実感できる業務の一つです。ぜひ、地味で地道な目録作成の大切さと奥深さにも注目してください。
暑い時期の受講は大変だと思いますが、お互い少しでも職人に近づけるよう、一緒に楽しく学びましょう。
松山 巌:玉川大学教授
目録規則とは,「こういうときはこういう風に記録する」というルールの集まりです。日頃利用している図書館のOPACも,こういったルールに則って作成されています。
初めて見た人は,こんなに細かい規則はとても覚えられないと思うかもしれませんが,全部覚える必要はありません。忘れたら規則集(NCR)を見れば良いのです。
ただ,見ても書かれていることが理解できなければ意味がありません。規則の意味を理解すれば,覚える負担もぐんと減ります。世の中にはいろいろな決まりがありますが,法律にしても,スポーツのルールにしても,それぞれの「決まり」が決められた理由・背景が分かれば,自分が納得してルールを理解することができるようになります。
というわけで,私の授業では,「なぜそう決められているのか」に(少し)こだわってみたいと思っています。「余計な理屈はいいから,そのぶんもっとテキストをたくさん進んでくれ」という人もいるかもしれませんが,丸暗記では応用が利きません。実際の目録作成では,NCRに決められていない事例に出会うこともあります。そのときに,自分で考えて合理的な記録の仕方を判断しなくてはなりません。その力を付けてほしいと思うのです。
また,新しい目録規則(NCR2018)では,従来の目録規則になかった独特の用語が多用されていますが,それらについても,できるだけ平易に説明していこうと思います。
どうか,「なぜ?」と思う心を大事にしてください。
佐藤 翔:同志社大学教授
どれだけ膨大なコレクションがあっても、組織化されないままであればほとんど探索は不可能になり、宝の持ち腐れとなります。利用しやすく、検索しやすくコレクションを組織化すること、それも実行可能な時間とコストで実現することは図書館の要です。
理論的背景を理解した上でその実務に取り組める能力を有することは図書館司書に不可欠なのですが、教科書を読んでいてもなかなか実感を持って取り組むことは難しい分野でもあります。この科目では情報資源組織の中でも目録について、なるべく具体例を踏まえつつ、実感を持って「なぜそうした方がいいのか」を理解しながら習得していただきたいと考えています。短期間ではありますが一緒に取り組んでいきましょう。
*先生のHP等はこちら
 情報資源組織演習(分類)
情報資源組織演習(分類)
竹之内 禎:東海大学准教授
図書館にある本の背中には、数字を書いたシールが貼ってあります。あの数字は、膨大な資料を図書館のどこに配架するか、その「所在地」を示す記号で、これが資料の整理と検索のための手がかりになります。この科目では、テーマ別に分類番号を与えるための特別なルール(資料分類法)について学びます。
また、資料を検索するための「検索用キーワード」の与え方も学習します。検索する利用者のことを考えて、適切な検索用キーワードを与えていきます。
演習は毎回が知識の積み重ねになりますので、極力欠席しないように体調に気を付けて、楽しんで学習して参りましょう。
藤田 節子:八洲学園大学講師
情報資源の組織化は、図書館の中でも根幹をなす業務です。『日本十進分類法』や『基本件名標目表』を学ぶだけでなく、それをひとつの実例として、あらゆる情報を組織化する能力を持つことが図書館員に求められています。演習をとおして、そのことを理解していただければ嬉しく思います。
暑い夏ですが、共に楽しく学びましょう。
田嶋 知宏:常磐大学准教授
図書館に関わる人たちは、情報資源を整理し、提供することを役割と自認してきました。
情報資源組織演習は、図書館における情報資源の整理方法の一端を学ぶものです。司書講習では、さまざまな内容を学び、実践すると思いますが、それぞれの知識やスキルは相互につながっています。
例えば、情報資源組織演習の分類や目録の知識は、情報サービスで図書を検索し、利用者に提供する際の基礎的な知識になります。それを意識しながら、この講習を乗り切っていただければと思います。
また、図書館を取り巻く環境は、技術・社会とも常に変化し続けています。このオンラインによる司書講習を通して、その変化に対応できる手がかりを皆さんに見つけていただければと思います。
坂本 俊:聖徳大学講師
図書館において利用者が求める資源や情報を提供するためには、図書館の保有する情報資源が適切に管理されていなければ適いません。
この授業で学ぶことになる分類は当に、図書館活動を支える根幹的な役割を担う知識・技術となるものであるため、ぜひ演習を通して学びを深めてください。
 図書館基礎特論Ⅰ
図書館基礎特論Ⅰ
中山 美由紀:鶴見大学講師
学校図書館との連携・協働が柱になっていない公共図書館はまずありません。学校図書館の利用者はだれですか。子どもと、さらに教職員もまた利用者なのです。学校教育と図書館との関わりを考えていただけるようにお話していきたいと思います。
事前にテキストに挙げたもののほか、東京学芸大学の「先生のための授業に役立つ学校図書館活用データベース 」や、鳥取県立図書館の「学校図書館支援センター 」をよく見ておいてください。
 図書館基礎特論Ⅱ
図書館基礎特論Ⅱ
千 錫烈:関東学院大学教授
今回はオンデマンドでの配信授業になりますが、対面授業に負けない熱量で授業をしていきたいと思います。図書館に関する様々なトピックスを紹介していきますので、授業を通じて図書館へのさらなる興味関心を広げていってください。
 図書館基礎特論Ⅲ
図書館基礎特論Ⅲ
佐藤 翔:同志社大学教授
図書館の運営・サービスに役立つ知見を、科学的手法に用いて世の中に生み出すことを目的の一つとする学問が図書館情報学(図書館学)です。この司書講習を担当する先生方も図書館情報学の研究者でもあり、それぞれ専門のテーマを持って研究に取り組まれています。その知見を背景に授業も担当されているわけですが、司書講習の授業内では図書館情報学がどんな研究をおこなっていて、どういった成果を生み出しているのかを直接、聞く機会はなかなかないかと思います。
その中で本授業担当は比較的キャッチーというか、図書館現場に限らず、図書館に興味がある人の多くが関心を持ちそうな、素朴な疑問を扱う研究をしばしばおこなっています。例えばどんどん新しい本が出ているのに、なぜ図書館の本棚はいっぱいになって溢れないのか(あるいは、いつか溢れるのか)。図書館を訪れる人の数はどういう時に増え、どういう時に減るのか。図書館をよく使っているのはどんな人で、逆に使わないのはどんな人なのか、などなど……。こうした素朴な疑問を、図書館情報学ではどういうアプローチで研究していて、どんなことがわかっているのかを紹介しながら、皆さん自身にも図書館等で働く上で調査・研究が必要になったとき、取り組める能力の基礎を習得していただきたいと思います。
*先生のHP等はこちら
 図書館サービス特論
図書館サービス特論
望月 有希子:鶴見大学准教授
この授業では,公共図書館における高齢者サービスを取り上げます。普段公共図書館を利用する際には,高齢者が利用する施設・設備,資料,サービスなど図書館の様子を意識して見ておいてください。
夏の暑いなか大変だと思いますが,元気に司書講習を楽しんでください。
 図書館情報資源特論(人文)
図書館情報資源特論(人文)
石田 千尋:鶴見大学名誉教授
暑い夏、体調を崩さぬよう頑張って下さい。
 図書館情報資源特論(自然)
図書館情報資源特論(自然)
長塚 隆:鶴見大学名誉教授
現代の社会で大きな比重を占めている自然科学分野の専門資料について学びます。 コロナ禍のなかでリモートでのデジタル資料の提供はより進展しています。デジタル資料の活用や資料の背景にあるトピックなどにも触れながら進めますので、授業に積極的に参加して、多くのことを得るように期待しています。
図書館総合展での講演も参考にしてください。
*先生のHPはこちら
 図書・図書館史
図書・図書館史
中山 愛理:大妻女子大学准教授
現在の図書館は、多様な変化に直面しています。特に、多様な記録媒体(媒体さえないものもある)やサービスが次々に出てくるように思うかもしれません。このような、図書館の新しい事象は、急に出現したわけでもありません。これまでの図書館の長い歴史の中で育まれてきたものです。メディアや図書館の歴史を学ぶことを通じて、図書館のこれからを冷静に見つめる力をもっていただければよいと思います。この科目を受講されない方も、ほかの科目で、記録媒体や図書館の歴史について、言及されることがあるかと思います。そうした言及の中から、現在の図書館につながることを見出していただけると、現在、そして将来の図書館を考える視点になると思います。
最後に一言。暑い夏の講習は、大変ではありますが、その分、得るものも大きいはずです。ぜひ、楽しく学んでください。